それはなんの変哲もない封筒から始まった・・・それが僕のすべてを変えてしまった。 「ただいま」 学校から帰った僕は、いつものようにポストを覗いて、入っていた封筒をいくつか抱えて家のドアをあけた。家の中は静まり返っていた。 「ただいま」僕はもう一度声をかけた。いつもならお母さんが”おかえり”って言ってくれるはずなのに・・・ 「お母さん?」持っていた封筒をリビングのテーブルの上に置いて、僕はお母さんの姿を探した。 「お母さん、いないの?」キッチンにも、どこにもお母さんはいなかった。庭には干しっぱなしの洗濯物が少し冷たくなってきた風に揺れていた。 「もう・・・しかたないなぁ」僕は洗濯物を丸めて抱えると、部屋のなかに放り込んだ。 「また・・・どっかで井戸端会議の真っ最中なんだろな」決して初めてじゃない。そうそうあることでもなかったけど。でも・・・ 「洗濯物まで干しっぱなしにしたままなんて・・・」 僕は冷蔵庫から牛乳を取り出して、ガラスのコップに注いだ。リビングに戻ってそれを一口飲む。テーブルの上に置いた封筒を一つ一つ見ていく。ほとんどはダイレクトメール、雑誌の申し込みとか、お店の広告とか・・・でも、一つだけ、宛名のない封筒があった。 「なにこれ・・・」茶色い、なんの変哲もない封筒・・・僕はそれを日にかざしてみる。べつに変わったところはなにもない。ただ・・・封はしてなかった。僕は中をのぞき込んだ。なんとなく、少し悪いことをしているような気がした。お父さんかお母さんの秘密を盗み見ようとしているような、そんな気が・・・ 封筒の中には紙が折り畳まれて入っている。何気なくあたりを伺う。そして、その紙を取り出して広げてみた。 その文面は見たことがあった。ただし、テレビで、だけど。実際に見るのは初めてだった。一文字ずつ、新聞を切り抜いて作った手紙だった。 |
||
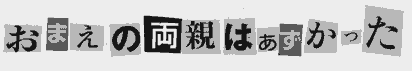 |
||
まさかね・・・・・でも、僕の手はふるえていた。 まさか・・・そんなはずはないよね。 普通、誘拐されるとしたら、子供がされるものであって、親が誘拐されるなんて、それも、『両親』が誘拐されるなんて、あり得ないよね。 そう思いながら、でも、僕は家の中をうろうろしていた。ソファに座っては立ち上がって、お母さんが帰って来やしないかと窓から外を見てみたり、意味もなく押入の戸を開いてみたり・・・ そんなとき、家の電話が鳴った。文字通り僕は飛び上がった。心臓が痛いくらいにきゅってなって、その場に凍り付いた。何度も呼び出し音が鳴る。 早く出なきゃ、切れちゃう・・・ようやく僕は電話に向かった。体がなんかいうことを聞かない。手足がぎしぎしきしみながら動いている感じだった。喉がからからに渇いていた。 「はい・・・湯原です」かすれる声を無理矢理絞り出した。はっきり分かるほどその声は震えていた。 「こちら、山鐘不動産と申しますが、今回は分譲マンションについてご提案差し上げたいお話がありま」 僕は受話器を置いた。 「ははっ・・・僕も馬鹿だな。犯人からの電話だなんて・・・あり得ないって」 僕は声に出してそういった。そして、そんなことを声に出している自分を馬鹿だと思った。電話の横の壁にもたれかかった。そして、そのままずるずると床に座り込んだ。座り込んだまま・・・じっとしていた。 やがて、夜の11時が過ぎた。まだ、お母さんもお父さんも帰って来ていない。もうあり得ないことだとは思っていなかった。僕は信じ始めていた・・・両親が誘拐されたことを。 そのまま、僕は朝まで電話の横に座っていた。時々立ち上がって受話器を取り上げた。警察に電話しようとした。でも、すぐに受話器を戻した。座り込む。また立ち上がる。受話器をとる。おばあちゃんの家の電話番号を押す。でも、最後まで押す前に受話器を戻す。座る。立ち上がる。玄関まで行って、耳をすましてみる。ドアを少し開けて外を見てみる。誰もいない。電話の横に戻る。座る。すこしうつらうつらする。なにか物音がした・・・ような気がした。音がした方に行ってみる。居間のテーブルの上に置きっ放しにしてあった携帯のランプが光ってる。あわてて携帯をつかんで画面を見る。メール着信・・・急いでメールを見てみたけど・・・ただの迷惑メール。携帯をポケットにつっこむ。また電話の横に戻る。座る・・・ 結局僕は朝までそこにじっとしていた。どうしたらいいのか分からなかった。 学校に行くべきかどうするか少し考えたけど、こんな時に学校なんて・・・と思って今日は行かないことにした。電話を台から廊下におろして、その横にごろんと寝ころんだ。眠かった。立ち上がって、僕の部屋のベッドから枕を持ってきて、また横になった。電話がかかってきたらすぐに出られるように、電話の横で少し眠ろうとした。でも、目を閉じるとあの手紙がちらついた。眠れなかった。眠いのに、なんかどきどきして眠れない。目を閉じて、どうするか考える。なにも思いつかない。とにかく、警察には電話はしないことにする。おばあちゃんの家にも電話しない。ひょっとしたらもうそろそろ帰ってくるかもしれないし。もうちょっと待ってみよう。もうちょっと待ってみよう。もうちょっと・・・もうちょっと・・・・・ 突然の電話の呼出音に僕は飛び起きた。立ち上がって電話の置いてある台の上に手を伸ばそうとして・・・床におろしたのを思い出した。しゃがみ込み、受話器を取った。 「も、もしもし・・・」 「おぉ、湯原か? 西本だ」学校の先生だった。少しほっとした・・・ような気がした。 「どうしたんだ、今日は?」そう言えば、無断で学校休んでるんだった。 「あの・・・ちょ、ちょっと風邪ひいたみたいで」 「そうか。今、ご両親は?」 一瞬、すべてを話したい衝動に駆られた。先生に、おかしな封筒がポストに入っていたこと、両親が帰ってこないことを話したいと思った。でも、僕はそれをしなかった。 「お父さんは仕事、お母さんは・・・今買い物に行ってます」 「それじゃ、あとでいいから、お母さんから学校にちゃんと連絡していただくよう、伝えてくれるか?」 「はい、すみません」 「じゃ、今日はゆっくり休んで、明日は学校出て来いよ」 「はい」 「じゃ、お大事に」 「ありがとうございます」受話器を戻す。ずっとしゃがんだまま話をしていた僕は、床に座り込んだ。 「どうしよう・・・」そうつぶやいた。そのとたん、また呼出音が鳴る。心臓が爆発しそうになった。 「はい、湯原です」受話器の向こうから、なんだか暗い空気が漂ってくるような気がした。 「もしもし?」しばらくは何の声も聞こえなかった。喉が乾く。受話器を握りしめる手に力が入る。 「手紙は見たな?」低い男の声だった。心臓のどきどきが、体全体に広がっていく。 「は、はい・・・」そう答えるのがやっとだった。 「警察や他の人には言うな。わかってるな」 「はい」舌がからからになった口のなかにくっついて、うまくしゃべれない。 「お前は常に監視されている。いつ、どこでなにをしているのか、全部わかっている」何かを読んでいるような、そんな感じの口調。受話器を握りしめる手が痛む。 「おかしなことをしたら、お前の両親を殺す」 「お、お母さん、お母さんは?」急に頭のなかにお母さんの顔がはじけた。 「お母さんはそこにいるの?」受話器を顔に押しつけて、僕は大きな声で叫ぶ。 「言うとおりにしたら、いずれ返してやる」男が言った。 「また連絡する」そして、受話器の向こうの声は聞こえなくなった。 「もしもし、もしもし、もしもし・・・・・」僕は受話器を握りしめ、叫び続けた。でも、何の答えも返って来なかった。受話器を握った手が汗をかいていた。そのまま壁にもたれ、目を閉じた。なにがどうなったのか、訳がわからない。僕はどうすればいいのか・・・ どこかで何かがうなり始めた。また僕の心臓が飛び跳ねた。うなり音は、僕の携帯からだった。マナーモードにしたまま、床の上においてある携帯が、小さく振動していた。携帯を手に取る。メールが来ている。タイトルのない、本文だけのメール。 ”普段通りの生活をしろ。学校にも普段通り行け”そう書かれていた。僕は発信者のアドレスを確認した。けど、それは僕自身のアドレスだった。僕のアドレスから僕の携帯にメールが来ていた。間違いない、さっきの奴だ。さっきの奴が、メールで僕に指示してきたんだ・・・ また、携帯が震えた。またタイトルのないメール。発信者は、僕。 ”警察、学校、友達、その他のだれにも言うな。言ったら両親とお前も殺す” 僕は携帯を閉じた。そして、携帯を両手で握ったまま床に座り込んだ。 「おなかが空いた」そう言えば、昨日からなにも食べていなかった。携帯を開いて時間を見る。もう午後7時過ぎだった。キッチンに行って何か食べ物を探してみる。朝食用の食パンを焼く。牛乳をコップに注ぐ。テーブルに座って食べる。けど、おなかは空いているけどなかなか食べられない。なんとか半分を牛乳で流し込む。そして、少しだけ泣いた。 翌朝、携帯の着信音で目が覚めた。僕はキッチンで眠っていた。また携帯にメールが来ていた。 ”いつものように学校に行け。おかしな真似はするな。キッチンで泣くだけではすまなくなるぞ。常に監視されていることを忘れるな” 思わず回りを見回す。僕が昨日、ここで泣いたことを知っている。ここが見えるところに犯人はいるんだ。窓の方へ近づき、あちこち見回してみた。それらしい人影とかそういったものはない。と、また着信音がした。 ”見回しても無駄だ”その画面をみたまま僕はテーブルに座り込んだ。監視されている。どうやってなのかはわからないけど、でも、確かに僕は常に監視されている・・・ あいつの言うとおり、普段と同じように僕は学校に向かった。でも、誰とも話をする気はなかった。1日中、下を向いていようと思った。 学校に着く直前に、また携帯が鳴った。 「電源は切るな。マナーモードにしておけ」そうメールに書いてあった。僕はその通りにした。 午前中は特になにも起こらなかった。ただ、僕がいつもと違って誰とも話さなかっただけで・・・ 給食も喉を通らなかった。 そして、午後の国語の時間、携帯が震えた。他の奴に見つからないようにして、僕は携帯を見た。 「ペニスを出してオナニーしろ」 僕は迷った。でも、やがてズボンの上からおちんちんをさわり始めた。なかなか大きくならなかったけど、やがて僕のおちんちんは大きく堅くなっていった。 ズボンからそれを出すのは勇気がいった。でも、命令に従わないと、お母さんとお父さんが殺される・・・回りはみんな僕のことなんか見ていない。先生に指名されたやつが立ち上がって教科書を読んでいる。みんな、教科書を見ている。僕は机の下で、ズボンのチャックを下ろしておちんちんを引っぱり出した。先生も、他のみんなも気が付いていない。僕はゆっくりとおちんちんをしごきだした。 「じゃ、次は・・・湯原」 「え・・・は、はい」突然名前を呼ばれて僕は焦った。机の下で、おちんちんが勃起したままだった。あわてて無理矢理ズボンの中に押し込む。ちょっとチャックが当たって痛かったけど、それでもなんとか押し込んだ。 「湯原、なにしてるんだ? 早く続きを読みなさい」 「は、はい」先生がせかす。その声で、みんなが僕の方を見る。僕はなんとかみんなに見つからないうちに、ズボンのチャックを閉めることができた。あわてて立ち上がると、体が机と椅子に当たってがたがたと大きな音がした。 「えっと・・・あの・・・どこですか?」誰がどこを読んでいたのか全然聞いていなかった僕は、先生に尋ねた。 「まったく・・・ちゃんと聞いてなかったのか? 56ページの3行目だ」 僕はあわててページをめくり、3行目から読み始めた。勃起したおちんちんを机に押しつけて、ズボンの膨らみを隠しながら・・・ 僕が読み終えるのとほぼ同時にチャイムがなった。 家に帰ると、すぐにメールが来た。 「命令に背いてオナニーをやめた。その結果どういうことになったのか教えてやる」そして、画像が付いていた。少しピンぼけの画像には、指が写っていた。指だけ・・・手のひらについているのではなかった。指の根本は黒っぽい血だまりになっていた。僕はなにが起きたのか理解した。お母さんの指だ、直感的にそう思った。お父さんの指ではない、お父さんの指はもっと太かったはずだ。僕が命令に従わなかったから、あいつはお母さんの指を切断した・・・ でも・・・あのとき、オナニーを続けろというの? みんなの前で、先生の前で、立って教科書を読みながらオナニーを続けろというの? 出来ない。出来るわけがない。でも・・・ それをしなかったから、お母さんの指が・・・・・僕はどうすればいいの? 僕は、命令に従うしかないの? リビングルームのテーブルに突っ伏して、僕は頭を抱えた。お母さんの指を切断されたショックと、あいつの命令であれば、みんなの前ででもオナニーしなきゃならないという不安で僕の体は震えていた。 翌日、学校には行きたくなかった。けど、行かないわけにはいかなかった。メールが来たから。 その日は1日吐きそうな気分だった。もちろん給食も食べられなかった。そして、給食が終わった昼休み、僕はメールに書かれていた命令を実行した。僕は教卓の方に向かって歩いた。体が思い通りに動かない感じだった。教卓の前に立つ。ベルトに手をかける。でも、そこで手が止まる。 「湯原、なにやってんだよ?」誰かが僕に声をかける。でも、誰が言っているのかわからない。なんだか頭のなかでみんなの声がぐるぐる回っている。僕はのろのろとベルトをはずした。そして、ズボンとトランクスに指をかけて、一気に膝までおろした。 「うわっ」誰かが大きな声を出す。 「きゃぁ」女子の誰かが悲鳴を上げる。 僕はおちんちんをつかんでオナニーを始めた。今回はイくまでやめる訳にはいかない。みんなに見られながらイって、自分が出したものを舐めてきれいにするまで、やめるわけにはいかなかった。携帯の命令は絶対だった。 みんなはそんな僕を遠巻きにして見ていた。女子のほとんどは教室を飛び出していった。教室に残っている女子も、顔を両手で覆ったり、後ろを向いていた。みんなが口々になにか言っていた。でも、僕はそんなことにかまっていられない。早くイかないと・・・きっと誰かが先生を呼んでくるから、それまでにイって、そして自分が出した精液を舐め取らないと・・・そうしないと、お母さんが・・・ でも、なかなかイけない。焦れば焦るほど、気持ちが萎えてしまう。萎えそうになるおちんちんを、無理やりしごいて勃起させる。こんな辛いオナニーは初めてだった。半分目を閉じて、なんとか早くイこうとする。でも・・・ ふと顔をあげた。ある奴と目があった。そのとたん、僕は自分のしていることの恥ずかしさを強烈に感じた。そいつは僕を見つめていた。悲しそうな顔で、僕をずっと見つめていた。小学校のころからずっと仲がよかったそいつ・・・親友、浩之が、僕を見ていた。 そのとたん、なにかが僕のなかでわき上がり、強烈な快感となっておちんちんからほとばしった。精液が勢いよく飛び散った。この瞬間・・・僕がイく瞬間も、ずっと浩之に見られているんだ・・・そんなことを思いながら、2回、3回と僕のおちんちんは精液を吐き出した。僕はまだ勃起しているおちんちんをにぎりしめながら四つん這いになって、床に飛び散った自分の精液を舐め始めた。 「舐めてやがる」 「うげぇ、気持ち悪わりぃ」 そんな声が聞こえた。でも僕はやめなかった。先生が僕を背中から羽交い締めにするまで、ずっと僕はやめなかった。 先生にはいろいろ聞かれるんだろうと思っていた。どう答えようか考えていたけど、答えは思いつかなかった。先生に羽交い締めにされて、下半身裸のまま、僕は保健室に連れて行かれた。連れて行かれる最中、僕は泣いていた。悲しくはなかったけど、泣いていた。先生は僕をベッドに寝かせると、なにも言わずに保健室を出ていった。やがて、僕の服と鞄を持って戻ってきた。そして、保健の先生に、落ち着いたら家に帰すように言って、出ていった。自分がみじめだった。でも・・・お父さん、お母さんのために・・・・・ 一人でとぼとぼと家に帰った。誰もいない家で、僕はコップに水を入れて、キッチンのテーブルに座ってそれを飲んだ。冷蔵庫のなかはほとんどからっぽだった。なにか食べ物を買ってこないと・・・そう思ったけど、体が動かなかった。僕はぼんやりと座ったまま、なにを考えるでもなく、時間が過ぎていくのに身をまかせた。 どれくらい時間がたったのかわからないけど、僕はチャイムの音で我に返った。誰かが玄関のチャイムを鳴らしていた。 「お母さん!」僕は飛び上がるように玄関に向かった。でも、すぐに気が付いた。お母さんなら、チャイムなんか鳴らさない。鳴らす必要なんかないってことに。 玄関の外には浩之が立っていた。なんとなく目を合わせにくいのか、ずっとうつむいていた。 「今、いい?」小さな声でそう言った。僕は浩之を家の中に招き入れた。 キッチンのテーブルに座っても、浩之はなにも言わなかった。でも、僕にはわかっていた。今日、学校でのことで来たんだって。だから、僕もなにも言わなかった。このまま二人ともなにも言わないまま、なにも聞かないまま浩之には帰って欲しかった。そうはいかない、というのもわかってたけど・・・ 「何であんなことしたんだよ・・・」浩之はうつむいたまま、小さな声で、つぶやくように言った。 「コーラでいい?」僕はごまかそうとした。椅子から立ち上がって、冷蔵庫のほうに行こうとした。 「そんなのいらないから、ちゃんと答えろよ」うつむいたまま、でもその声は怒っていた。 しばらく、なにも答えられなかった。どう答えればいいのかわからなかった。もちろん、本当のことは言える訳がない。でも、浩之は怒ってる。怒った浩之は、納得するまで僕を問いただすだろう。浩之のことだから・・・あいつのことはよくわかってる。あいつも、僕のこと、よくわかってるはずだ。 「別に理由はない、したかったからしただけだ」ごまかせる相手じゃないのはよくわかっていた。 「お前・・・人前でオナニーなんかしたいはずないだろ!」浩之の声が震えていた。 「なにがあったんだ? 言えよ」浩之が顔を上げた。真剣な顔だった。まっすぐに僕を見つめた。 「やりたかったんだよ、みんなの前で」立ち上がったまま、浩之の視線に捕らえられたかのように動けなかった僕は、そう言い切って冷蔵庫に向かった。冷蔵庫の扉を開けて、コーラを取り出す。コップに注いで、テーブルへと持っていく。浩之は、顔を落としてテーブルの表面を見ていた。僕はその前にコップを置いた。 「言えないなら言わなくてもいいよ。でも・・・」浩之はうつむいたまま言った。 「もうしないって約束して。あんなこと、お前らしくない」 浩之の気持ちはすごくうれしかった。でも、その約束は今の僕には出来なかった。今の僕は、誰になんと言われても、メールで命令されたことをこなさないと・・・ 「約束もしてもらえないの?」黙ったままの僕にしびれをきらしたのか、浩之の方から尋ねた。 「ごめん」僕は短く答えた。そして、二人とも無言でうつむいたまま、時間が過ぎていく。 しかし、そんな時間は長くは続かなかった。僕の携帯が振動し、それがテーブルに伝わって大きな音を立てた。僕の心臓がきゅっとなる。メールの着信・・・こんな時に。見たくなかった。 「携帯なってるよ」浩之が言った。浩之にとっては、無言の時間を終わらせるいいきっかけだったんだろう。僕はしかたなく携帯をつかんだ。 「そいつを犯せ」 短いメール、でも、そのメールは僕を突き落とす。 「どうかしたの?」浩之が僕に尋ねた。僕は、なにも言わずに立ち上がった。 こんなことしたくはなかった。でも、メールの命令に逆らったら・・・この前は指だった。次は・・・考えたくなかった。お母さんとお父さんのため・・・僕は浩之の椅子の後ろ側に回った。そして、後ろから浩之の体を抱きしめた。 「な、なに?」少し驚いたように浩之が言う。僕はそんな浩之の体を椅子から引きずりおろし、その体の上に馬乗りになった。 「な・・・どうしたんだよ?」浩之は自分が何をされるのか、理解できていない。僕はそんな浩之の口にむしゃぶりついた。そして浩之のシャツをたくし上げ、その体に手をはわせる。 「や、やめろよ、どうしたんだよ」浩之にもようやくなにをされるのか想像できたみたいだった。僕は無言のまま、浩之の服を脱がそうとする。そう。こうすれば、きっと浩之は僕に愛想を尽かしてくれる。もう二度と、僕に近寄らなくなる。そうすれば、きっと、もう、心配かけたり、巻き込んだりしなくてよくなる。だから・・・ 僕はまた浩之にキスをした。今度は舌を無理矢理ねじ込んだ。荒い息をしながら、浩之の口をむさぼった。できれば・・・僕を突き飛ばして、殴るなり蹴るなりして、この場から逃げ出して欲しかった。 だけど・・・急に浩之の体から力が抜けた。 「お前・・・なにがあったのか知らないけど・・・本当にお前がそうしたいのなら、いいよ」浩之が僕に抱きしめられながら言った。僕は、抵抗しようとしない浩之を前に、なにもできなくなってしまった。 「ほら・・・よくわからないけど・・・続きをしなよ」 浩之はなにか気付いているようだった。あのメール、その後の僕の行動・・・考えてみたら、気付かれても当然だった。僕は浩之を抱きしめ、耳元で小さくつぶやいた。 「ごめん・・・犯す」 浩之は抵抗しなかった。僕にされるがままに服を脱がされた。四つん這いになった浩之を背後から僕は犯した。やり方もよく分からないまま、無理矢理・・・ 僕は浩之の中に出してしまった。浩之はひたすら痛みをこらえているようだった。けど、「やめろ」とは言わなかった。あの時・・・浩之が家に来たとき、なんで追い返さなかったのか、僕は後悔していた。 「シャワー、浴びよう」そう言い出したのは浩之のほうだった。 「うん」僕等は裸のまま、バスルームに向かった。 二人でシャワーを浴びる。浩之が僕の体を洗ってくれる。僕も、浩之の体を洗う。と、急に浩之が僕を抱きしめた。二人の頭の上からシャワーが降り注ぐ。そんな状態で、浩之が僕にささやいた。 「なにがあったの?」 また僕はごまかそうとした。 「ごまかさないでよ。もう、僕だって・・・こんなことされたんだから」 僕はしばらく黙っていた。頭からシャワーを浴びたまま、なにも言えなかった。そんな僕を、浩之はずっと抱きしめていてくれる。あんなことをした僕なのに・・・ やがて、僕は全てを話した。誘拐のこと、電話のこと、メールのこと、そしてさっきの命令のこと・・・ 「だから、もう僕には近づかないで。これ以上巻き込みたくない」 「やだよ。お前一人でなんとかなるもんじゃないだろ?」 「でも、警察とかにも言えないし、いつも監視されてるみたいだし・・・」 「だったら・・・なおさらだよ。人を巻き込んでおいて、勝手なこと言うなよ」 「ごめん・・・」 「謝るなよ。僕はお前の味方だから」そして、浩之がぎゅっと僕を抱きしめてくれる。そして僕等はキスを交わした。本気のキスだった。 バスルームから出てくると、僕の携帯にまたメールが来ていた。僕と浩之がしているところの画像が添付されていた。思わず僕は、その画像が撮影されたと思われる方向を振り返った。いろいろと目を凝らしてみても、カメラとか、誰かが見ているとか、そんな様子はなかった。浩之が、そんな僕の手から携帯を奪い取った。 「あ、だめっ」取り戻そうとしたけど遅かった。浩之は、送られてきた僕等が裸でしている画像を見つめた。 「ホントに・・・監視されてるんだ」浩之がそうつぶやいて、携帯の画面を閉じる。と、またメールが届いた。浩之はそれを見た。 「風呂場なら大丈夫とでも思ったか? お前の名前と携帯のアドレスを知らせろ」 そのメールを浩之が僕に見せる。そして、浩之自身が名前とメールアドレスを入力して返信した。 「ごめん・・・巻き込んじゃって」僕は浩之にわびる。これから、たぶん僕だけじゃなくて、浩之も命令されるんじゃないかと思う。そう思うと・・・浩之もあんな恥ずかしいこととかさせられるのかと思うと、本当にすまないと思った。 「だから・・・なんで謝るんだよ」浩之が笑ってそう言ってくれる。 「僕、お前のためならなんだってするって。心配すんなって」そして、また僕をぎゅっと抱きしめてくれた。 「僕、ホントはお前とやれてうれしいんだ」そして、今度は浩之が僕を床に押し倒そうとした。 「だ、だめだって。監視されてるんだから」僕はあわてて言った。 「どうせさっき見られたんだし・・・もういいじゃん、見られててもかまわないよ」 僕等はもう一度裸になって抱き合った。今度は前みたいに無理矢理じゃなく・・・そして、今度は僕が浩之に入れられた。背中に浩之の体温を感じながら、お父さんとお母さんがいなくなって、ずっと一人で張りつめていた気持ちが、ゆっくりと楽になっていった。 翌日、僕はいつもの通り学校に行った。その日の朝はメールは来なかったけど、きっと何か命令されることを覚悟しながら。でも、ここ数日のなかで一番気持ちは楽だった。浩之がいてくれるから。すべてを知って、僕がどんなことしても理解してくれる浩之がいてくれるから。そう思うと、早く浩之の顔が見たくなる。いつもより少し早足で、僕は学校に向かった。 教室に入ったとき、なにかいつもと雰囲気が違っていた。みんなが教室の後ろに集まって、何かを取り囲んでいた。 「おはよ・・・」僕は自分の机に鞄を置いて、みんなの方に近寄った。みんなは輪になって何かを取り巻いていた。みんなの背中越しに、その輪の中心を見る。そして、まるでハンマーで頭を殴られたみたいな衝撃を受けた。 「ひ、浩之・・・」 輪の中心にいたのは浩之だった。浩之は全裸で教室の床に寝そべっていた。そして、足をあげて・・・手でお尻の穴にディルドを出し入れしている。まるで、勃起したおちんちんをみんなに見て欲しいかのように足を広げて、ディルドをお尻の穴の奥まで差し込み、そしてそれを引き抜いて、また差し込んでいた。みんなはなにも言わずにその様子を見ている。異様な雰囲気の中、誰もなにも言わなかった。 と、携帯が震えた。 「お前はなにも言わずに見ているんだ。いっさい手を出すな」 メールはそう命令していた。昨日、あんなことで巻き込まれて・・・いきなり今日、こんな恥ずかしいことをさせられている浩之・・・僕は両手をぎゅっと握りしめて、浩之に駆け寄ってやめさせたい気持ちを押さえた。お父さんとお母さんが生きて帰ってくるために・・・浩之だって、きっとそう思って耐えてくれてるんだ、そう思うと、僕にはメールの命令に逆らうことは出来なかった。 やがて、浩之は射精した。昨日の僕と同じように・・・いや、昨日の僕は下半身だけ裸だったけど、浩之は全裸で自分が出した精液を舐め取っていた。四つん這いで床に飛び散ったのを舐めると、アナルが丸見えになる。そこはてらてらと光っていた。それを見て、僕は勃起してしまう。こんな時なのに・・・浩之はきっと辛くて恥ずかしくて逃げ出したくて、でもどうしようもなくて、仕方なくやってるのに・・・しかも、僕の両親のために。 授業が始まるころには、浩之は服を着て、机に座っていた。でも、表情は堅く、まわりのみんなも浩之を避けているようだった。でも、それは僕も同じ。昨日のことをみんな忘れた訳ではなかった。 辛い1日が始まっていた。 授業の最中も、僕はずっと浩之を気にしていた。昨日の僕と同じように、机の下でずっとオナニーしている浩之を。僕にはなにも命令メールは来ていない。浩之は時々メールを見ているようだったから、きっとあいつのところにはいろいろと来ているんだろう。なんで、僕じゃなくて浩之なんだ・・・そう思っても、僕にはどうすることもできなかった。 「先生」椅子ががたっと音をたてた。浩之の声だった。 「ん、なんだ?」先生は、黒板に問題を書きながら、背中越しに答えた。 「その・・・オナニーしてもいいですか?」それはなかばやけになったような大きな声だった。クラス全員が浩之を見つめた。 「授業中に冗談言うな」相変わらず黒板に書きながら答える先生。でも、立ち上がった浩之のズボンからは、勃起したおちんちんが突き出されていた。片手で軽くそれをこすりながら、浩之は先生に言う。 「でも、もうイキそうなんです」 静まり帰っていた教室が急に騒がしくなった。 「静かに・・・お前、なにやってるんだ」ようやく振り向いた先生が言葉に詰まる。あわてて浩之の方に歩み寄って、おちんちんをこする手をつかんでやめさせる。 「ふざけるのもいい加減にしろ」そして、先生はそのまま浩之を椅子に押しつけるようにして座らせて、おちんちんをしまわせた。 「なに考えてるんだ、授業中に・・・」先生の声が怒りに満ちていた。 「先生とセックスすること」浩之が先生の質問に答えた。 「な、なんだと?」一瞬、先生が握り拳を振り上げた。しかし、それを振り下ろすことはなかった。 「神田、あとで職員室に来なさい」そして、先生は教壇のところに戻った。 浩之はだまってうつむいていた。 放課後、僕は職員室の前で、浩之が解放されるのをずっと待っていた。1時間くらいしてから、ようやく浩之が出てきた。 「大丈夫?」なんて声をかけたらいいのかわからなかった。とりあえず思いついた言葉を口にした。 「別に大丈夫だよ」浩之がそう答える。でも、全然大丈夫そうではなかった。 「ごめん・・・僕のせいで」それ以上、なにも言えなかった。もう、こんなことは終わりにしたい、そう強く思った。でも、もしそうしたら、僕のお父さんとお母さんが・・・ 僕等は学校を出て、家に向かってゆっくりと歩いた。浩之の顔を見ることができなかった。なにか言わなきゃ、とは思うものの、なにを言えばいいのか分からなかった。 「あの・・・ほんと、ごめん」さっきから同じことばかり言ってる、自分でもそう思ったけど、それ以外の言葉が見つからない。 「平気だって。昨日にくらべりゃたいしたことないさ」浩之が顔をあげる。なんだか、疲れた顔をしている。 「ごめん、昨日のことはほんとに」昨日、家で浩之にしたことは後悔していた。謝ってもすむことじゃない、とは思うけど・・・でも、謝るしかなかった。 「そうじゃないって」浩之が制した。 「お前だから、あんなことになってるって知ってるから全部隠さずに言うけど、お前の家から帰る途中でメールが来たんだ。夜、市民球場のトイレんとこに来いって」 「行ったの?」少し心配になる。 「あたりまえじゃん。でないと、マズいだろ?」 「そりゃそうだけど・・・」悪い予感がした。 「そこで犯された。3人くらいいたのかな。そいつらに」 ショックだった。僕にはなにも言えなかった。単純に巻き込んじゃったとしか思ってなかった。でも、実際はそれ以上のことになっていたんだ。 僕がいろいろ命令される代わりに、浩之がいろいろと命令されてるんだ。命令を聞かないと、僕の両親が、浩之のじゃなくて、僕のお父さんとお母さんが殺されると知っている浩之に、僕の代わりに恥ずかしいことやひどいことして・・・僕の体から力が抜けていった。立っていることが出来ずに、その場にしゃがみ込んだ。 「ごめん・・・僕のせいで・・・そんな目にあってたなんて・・・」 「気にすんなよ」浩之もしゃがみ込んで、僕の顔をのぞき込んで言った。泣きそうになっている僕の肩に手をかけて、ぎゅっとしてくれる。 「もう・・・」その先の言葉が出てこなかった。(もう、いいから)そう言いたかった。これ以上、浩之が辛い目にあうのはいやだった。だから、もう、いいからって言いたかった。でも、そうしたら僕のお父さんとお母さんが殺される・・・ 「大丈夫だから、な。一緒にがんばろ、な」僕の気持ちがわかっているような、そんな感じだった。僕は浩之に抱きかかえられるようにして立ち上がった。そのまま浩之は、僕を誰もいない家まで送ってくれた。 翌日も、あまり変わりない状況だった。 浩之は、トイレの前にずっと立っていた。首から「性処理します」って看板をぶら下げていた。もちろん、誰からも相手にされない。中には面白がっていろいろ言うやつもいたけど、ホントに性処理するところまでいく奴は誰もいなかった。 「あの・・・」そんな浩之に僕は声をかけた。 「いらっしゃいませ。口でしますか? おしり使いますか?」そう言えって命令されてるんだろう。 「いいから、中で」僕は浩之の手を引いて、トイレの個室に入った。他の奴らが興味深そうに少し距離をおいて取り巻いている。僕は鍵を閉めた。 「大丈夫?」小声で聞いた。 「うん。昨日は少し慣れたし」浩之が、僕の前にしゃがみ込んだ。 「そんなことしなくてもいいよ」僕は浩之の脇に手を入れて、体を引き上げた。 「また犯されたの?」 「大したことないよ。それより」また浩之がしゃがみ込む。 「だから、いいって」僕はまた立たせようとしたけど・・・ 「命令なんだから、やらせろよ」浩之が僕のズボンのチャックに手をかけた。浩之の手が僕のおちんちんを引っぱり出し、そしてそれを口にくわえた。 その夜は、僕は浩之と一緒だった。浩之は、市民球場のトイレの前で、あの看板をぶら下げて立っていた。僕は、少し離れたところで身を隠しながらそれを見ている。それが命令だった。時々、男に手を引かれてトイレに入っていく浩之。浩之がなにをしているのか、なにをされているのか、僕は近づくことも許されていなかった。ただ、浩之がそうやって使われているという事実だけを見ていなければならなかった。 やがて、3人の男が浩之を取り巻いた。看板を指さし、笑い、その場で浩之の体に触れていた。そのまま一人が浩之を羽交い締めにし、トイレの中に連れ込んだ。かなり長い時間、そいつらは出てこなかった。ようやく出て行ったあと、だいぶ時間が経ってから、浩之も出てきた。破れた看板を手に、それでもまたそこに立った。そのまま朝まで立ち続け、時々現れる男に使われていた。 そして明け方、僕の携帯が震えた。 「二人で球場の入り口のところに来い」 僕が顔を上げると、浩之も携帯を見ていた。僕はようやく浩之に近づくことができた、そして、二人で球場の入り口のほうに歩いた。 球場の入り口には1台の車が停まっていた。エンジンがかかったままだった。 「乗れ」そう書かれたメールが来る。僕等はこれまでそうしてきたのと同じように、命令に従う。車の中には男が二人。僕等は手を縛られ、目隠しをされた。もちろん逆らったりしない。やがて、車がどこかに走り出した。これからどうなるのか、どんな目に遭うのか・・・不安と同時に、ひょっとしたらお父さんとお母さんのいるところに連れて行かれるのかも知れないという、ほんの少しの期待もあった。 僕の顔に何かが押し当てられた。頭がくらくらした。意識が遠のいていく・・・たぶん、浩之も、同じよう・・・に・・・・・・・・・ 頭がふらふらする。体が揺れているようだった。 誰かがなにか言っている。なんだか聞き取れない。目隠しがはずされた。誰かが目の前に水の入ったコップを差し出している。僕はそれをつかんで一気に飲み干した。 頭がぼんやりしている。目の前の誰かがコップを持って行く。 「祐人」誰かが僕を呼んだ。その声の方向に目を向けた。浩之がいた。なんでここに浩之がいるんだろう・・・そして、ようやく意識がはっきりしてきた。僕等は車に乗せられて、目隠しされて眠らされたんだ。 「浩之・・・」そして、回りを見渡した。どこかの・・・いろんなものが置いてある部屋・・・むしろ倉庫・・・みたいなところだった。 「浩之」僕は立ち上がって浩之に近づこうとした。でも、足が動かない。ようやく自分の足に金属の足かせが付いてることに気が付いた。 「浩之、大丈夫?」大きな声を出したら、なんだか胸が痛い。 「ああ。お前は?」浩之の足にも同じような足かせがついていた。 「大丈夫。まだ体が揺れてるみたいだけど」 「あたりまえだよ。ここ、船の中らしいし」浩之が少し笑った。そう言えば、なんだか海のにおいがする・・・ 「僕達、どっかに運ばれてるみたいだよ」 「どこかって?」 「わかんないよ。みんな、外人みたいだし」そう言えば、さっき水をくれた人も、日本人っぽくはなかったっけ・・・ 「外人って・・・僕等、外国に連れて行かれるの?」 「わからないけど・・・たぶん」そこまで言ったところで、男達が数人部屋に入ってきた。僕の足かせをはずして立ち上がらせる。足に力が入らない。男達に引きずられるようにして、僕は部屋から連れ出された。 僕が連れて来られたのは、診療室みたいな部屋だった。口を開けさせられて中をのぞき込まれたり、瞼めくられたり、血を取られたり・・・でも、そこにいた人たちは全員日本人じゃなさそうだった。言葉もどこかの国の言葉、なにを言っているのか分からなかった。身振り手振りで服を脱げだとか、あるいは無理矢理口を開けさせられたりとか・・・そして、ベッドに横になれ、と。ベッドに横たわった僕の体の上にゴムみたいなのをかけられて、身動きできなくされる。そして、なんだかわからないけど点滴をされる。なにがどうなっているのか、さっぱり分からなかった。しばらくそうして点滴されたあと、またあの部屋に戻された。もちろん、足かせをつけられて。 「祐人」部屋に戻ると、浩之が心配そうに声をかけてきた。男達が部屋から出ていくのを待って、僕は浩之と話をした。 「なんかされたの?」足かせがついたまま、僕のほうに近寄れるだけ近寄って、浩之が尋ねた。 「なんか、健康診断みたいなことされた」僕もなるべく浩之の方に近寄った。でも、どんなにがんばっても、二人の間には2,3メートルくらいの距離があった。 「へぇ・・・僕はなんにもされなかったけど」 「なんだか、言葉通じないし、なにされてるのか全然わかんなかったよ」 「みんな、外人みたいだし・・・僕達、これからどうなるんだろ・・・」 「わかんない。この船にお父さんとお母さん、乗ってるのかなぁ」 僕達は、不安をまぎらわすかのように話をした。ホントは浩之と体を寄せ合って、あいつの体温を感じていたかった。そうしたら、ほんの少し安心できたと思うんだけど・・・ |
||
********** |
||
「無事に出航したようです。これで引き渡しが完了した、ということになります」校長室で、校長先生が一組の男女を前に、書類を広げた。 「契約では、この時点をもって売買成立ということですから、湯原さんの銀行口座には今日中に代金が振り込まれるはずです」 「本当に、いろいろとお世話になって」祐人の母親が校長先生に軽く頭を下げる。 「ほとぼりが冷めるまで、しばらくどこか海外に旅行でもなさるとよろしいでしょう。第二の新婚生活を存分に楽しまれてはどうですか?」校長先生が契約書を両親の方に押しやった。 「ええ、二人っきりでハワイあたりに1ヶ月ほど行く予定です。資金ならたんまりありますしね」祐人の父親は、契約書を軽く指ではじく。 「その間に、お宅に取り付けた隠しカメラや盗聴マイクをすべて撤去いたします。家の売買手続き、新居の手配、すべて我々のサービスに含まれておりますので、帰国された際にはすぐに新しい生活に入っていただけるよう手配いたします」校長先生は、まるで旅行代理店の窓口担当のような顔をしていた。 「あの、息子の記録の方は?」母親が尋ねた。 「そのことでしたら、西本先生がうまく処理して下さいます」校長先生は、部屋の隅に立っていた西本先生のほうをちらっと見る。 「記録上、祐人君は転校した、ということになります」西本先生が、両親の座っているソファに近づきながら言った。 「でも、それでは転校の手続きとかいろいろやっかいなんじゃないですか?」父親が、後ろを振り向いて西本先生に言う。 「そのあたりは、我々にお任せ下さい。そういう処理は手慣れておりますので」西本先生は笑顔で言った。教師というよりは、むしろ優秀な営業担当、といった感じだった。 「ま、後のことは心配なさらずに、厄介者がいなくなった開放感を十分楽しんできて下さい」 「そのことですけど・・・警察沙汰になったりは・・・」 「契約時に申し上げたとおり、我が校では、実はご両親がお子さんを嫌っている、というケースをこれまで何十件と処理してきました。嫌われた子供は、別の用途のために、主に海外の裕福な方達に買い取られていきます」校長先生は、立ち上がって校長室の中を歩きながらしゃべり始めた。 「我々は、お子さんを嫌っているご家庭で、将来的に不幸な虐待や事故が発生しないよう、そして、ご両親にとって、もっともよい方法をご提案差し上げている訳です。今回も、祐人君は、とある国の裕福な家庭に、養子として買われて行きました。日本にいては得られない、非常に特別な身分の家庭の養子としてです。祐人君にとって、幸せ以外のなにものでもないわけです。そして、ご両親にも一生かかっても手に入れられないような大金が入ってくる。私どもも、手数料で潤う。皆が幸せになれるシステムですよ」校長先生のプレゼンテーションは続く。 「皆が幸せになれるんです。いままでに手がけた何十件というケース、すべてにおいてです。完璧な処理、誰一人不幸にならないシステム。警察沙汰になる理由がありませんよ。お母さん」そして、ソファのうしろから、祐人の母親の肩に手をかけた。 「安心して第二の新婚生活を楽しんでいらっしゃい」 祐人の両親の顔に笑顔が広がった。彼らは校長先生、そして担任の西本先生と握手をして、学校を後にした。 |
||
3ヶ月後・・・ |
||
祐人は、大きな屋敷の一室で、ヘッドホンを付けていた。べつに音楽を聞いているわけではない。その国の言葉をこうして勉強していた。今では簡単な日常会話くらいならこなせるようになっていた。そんな祐人の肩に手が置かれた。 「お食事の支度が出来たそうです」浩之は、祐人のヘッドホンを少しずらして大きな声で言った。祐人は後ろに立つ浩之を振り返る。 「ああ、わかった。行くよ」 そう言って歩き出した祐人の少し後を浩之は歩く。 「でも、二人っきりのときは、前みたいに友達として接してくれたらいいって何回言わせるの?」祐人は浩之に苦情を言う。 「もう、くせになっちゃったんだよ」そんな浩之の答えに祐人は笑い声をあげる。広い廊下にその笑い声が響いた。 「じゃ、食事の後、僕の部屋に来て。また・・・Hしよ」声をひそめるでもなく、祐人は言った。 「全く・・・ぼっちゃまはいつまでたってもお下品なところは変わりませんね。誰かに聞かれたらどうするおつもりですか?」そう言って、浩之も笑った。 「だって、日本語分かる人誰もいないもん」祐人は浩之の方に手を差し出す。 「はいはい。どうせ私はおぼっちゃま専用の使用人兼性処理係ですからね」浩之はその手を握った。二人は広い屋敷の中、手をつないだまま食堂に向かって歩いた。 屋敷の主人は、食堂のテーブルの正面に座る少年を見て目を細めた。いい買い物だったと感じていた。見た目も良い。わずかな期間に言葉も覚え、頭も良さそうだ。そして、なにより健康だ。この家に買い取ったからには、一流の人間として育ってもらう必要がある。そのためには金を惜しむつもりはなかった。なぜなら、この子は当家の主人が将来、内蔵疾患をわずらった際の、スペアパーツなのだから。将来、主人の体の一部となるのだから、それにふさわしい人間になってもらわないと・・・金にあかせて世界中から主人にもっとも近い体質の少年を選りすぐった意味がない。 そして少年は、この屋敷で大切に育てられるのだった。いつか来るその日のために・・・ 食事の後、浩之は祐人の部屋をノックする。そして、部屋に入る。広くて明るい部屋の中で、二人っきりになる。浩之は、なんのためらいもなく全裸になる。その様子を祐人はじっと見ている。全裸になった浩之が、祐人の足下の床に正座する。 「ご主人様、どうぞお好きなようにお使い下さい」 この家に引き取られた祐人と、その世話をするための使用人である浩之。二人の身分の違いは明らかだった。しかし、今、彼らの関係はそうではなかった。所有者と性処理道具、それが二人だけになったときの彼らの関係だった。 「じゃ、今日は・・・掘ってよ」祐人がベッドの上に横たわる。 「はい、ご主人様」そして、浩之もベッドの上に上がる。祐人は四つん這いになる。浩之は、そんな祐人の服をゆっくりと脱がせていく。やがて、全裸になった祐人のお尻に顔を埋め、アナルを舐める。そして、ローションを付けた指をゆっくりと挿入する。 「ん・・・」祐人が声を出す。タイミングを見計らって、祐人は仰向けになり、浩之がその体ににじり寄って足を抱え上げる。そして、二人は一つになる。 「あ・・・はぁ」今まで何度となく繰り返してきた行為・・・少しずつ二人の動きが早くなる。 「あっ・・・あっ・・・」その動きに合わせて祐人があえぐ。手は自らのペニスをこすりあげる。 「ん・・・・ん・・・・」浩之も、声を漏らしながら祐人の体を突き上げる。 「あ・・・い、いきそう」浩之が思わず身分の違いを忘れてつぶやく。 「だめだよ、まだいっちゃ・・・命令だよ」祐人の手の動きが早くなる。 「あ、はい」体の動きを少し遅くする浩之。祐人のペニスをしごく手の動きが早くなっていく。 「あぁ・・・いく」今度は祐人がそう言う。浩之は、祐人のお尻に腰を打ち付けるようにして、その奥まで突く。 「ああぁ・・・」祐人のペニスから精液が勢いよく飛び散った。ほぼそれと同時に、浩之も祐人の体の奥に放出した。 浩之は、精液が飛び散ったままの祐人の体に自らの体を合わせる。そのまま、つながったままキスを交わす。 「いつものようにして」祐人がそう言うと、浩之は体を起こして、祐人の腹に付いた精液を舐め、自分の体に付いたのも指ですくい取って舐め取った。 そして、祐人の体からペニスを抜くと、その足を持ち上げる。祐人が少し力むと、祐人の体の中に放出された浩之の精液が、アナルからどろりと流れ出る。それも浩之はすべて舐める。 その後、二人はキスを交わす。浩之が口の中に溜めていた二人の精液を、口移しで分かち合う。長いキスが終わると、二人はベッドの上で体を寄せ合った。 「こうしていると幸せ・・・」浩之がつぶやく。 「性処理道具にされると幸せ?」祐人が言う。 「お前に使われるのなら・・・どっちが使われてるのかよくわからないけどね」浩之が笑った。 「いいの、お前となら・・・どっちでも」祐人はそう言って、浩之に軽くキスをした。そんな祐人を、浩之はぎゅっと抱きしめた。やがて、二人は眠りに落ちていった。 南国の照りつける日差しの中、久しぶりの二人っきりのバカンスを楽しむ男女がいた。二人は、息子と引き替えに手に入れた大金で、第二の新婚生活を思う存分楽しんでいた。幸せそうな二人には、後悔や不安といったものはみじんも感じられなかった。 <誘拐 完> |