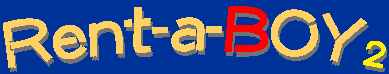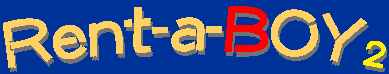年越しそばはいわゆる「もりそば」だった。
「ごめんね、海苔を買うの、忘れてた」
そう言いながら、そばを持ってくる祐樹。家にせいろみたいなものはないので、そばは適当な皿に盛りつけてある。
「じゃ、食べるか」
そばはもちろん店で買ったもの。つゆもそうだ。でも、祐樹と二人で食べるとなぜか美味しく感じる。
「うまいそばだな」
「うん」
二人でそばをすする。点けっぱなしのテレビに、年末の様子が映し出される。
「ね、この辺って、どこで初詣するの?」
祐樹が少し箸を止めた。
「そうだなぁ・・・歩いて行けるところに神社はあるけど、あんまり初詣って感じでは行かないなぁ」
俺は特に初詣を重んじる人間じゃない。そんなに神様仏様を信じてるわけじゃないし。まぁ、都合のいいときだけ信じる方だ。
「じゃ、おそば食べ終わったら、行ってみない?」
しかし、すでにかなり遅い時間だ。
「年越し参りしようよ」
大晦日の夜に行って、新年を神社で迎える、そんなことはもちろんやったことはない。
「寒いだろ」
「そりゃ寒いけど・・・着込んでいけば大丈夫だよ」
正直、面倒くさかった。しかし、祐樹はあきらめない。
「ね、一緒に行こ。二人でさ」
そう上目遣いで頼まれると、ちょっと嫌とは言いにくい。
「じゃ、とっとと片付けして、ちょっと行ってみるか?」
「うん!」
うれしそうに祐樹は頷いた。
「そういや、お前、服持ってきてるのか?」
朝来たときは、そんなに厚着をしていたわけじゃない。でもこれから出掛けるとなると、あの服装では寒いだろう。
「渉さんの、貸して」
「まあ、いいけど」
俺は取りあえず、いつも着ているセーターを祐樹に手渡す。祐樹がそれを着る。案の定、だぶだぶだ。
「別の、探そうか」
「いいよ、これで」
祐樹は平気だ。しかし、そのセーターを着たまま、祐樹の上着を着ようとすると、セーターが大きすぎて上着の中にセーターを押し込むような感じになる。上半身がもこっと変な形になっている。
「それ、どう見ても変だろ」
「そうかなぁ」
祐樹が自分の体を見回す。
「上着も貸して」
貸してやる。案の定、デカい。俺のショートコートがまるでロングコートだ。手は袖の遙か奥だ。
「それも変じゃん」
俺は笑ってしまう。
「ん、いいよ、これで」
祐樹は袖を振り回す。どういうわけか、この格好が気に入ったようだ。
「行こ!」
その格好のままで、祐樹は俺をせかした。
こんな時間、神社には誰もいないだろうと思っていたが、予想に反してかなりの人出だ。
「ほら、みんな年越し参りに来てるんだよ」
所々でかがり火のような火を焚いている。そんなかがり火の一つの前で、祐樹は袖をたくし上げて手のひらを前に突き出し、火に当たっていた。
「意外だなぁ・・・そういうものなのかなぁ」
俺も祐樹の横で火に当たる。
「お正月だもん」
まあ、普通の日の夜だったら、一人も人がいなくて、かがり火もなくて、灯りもなくて、かなり怖いだろうとは思う。それがお正月だと、こうなるわけだ。
「さすが、正月ってとこだな」
「そうだね」
二人で少し笑う。
「じゃ、お参り行く?」
祐樹が腕にはめた俺の腕時計を見て言う。もちろん、祐樹の腕にはゆるゆるだ。
「今何時?」
「あと2分」
「じゃ、急がないと」
俺と祐樹は並んで賽銭箱の前に立った。
(とりあえず・・・祐樹とあと2日・・・)
俺は何を祈るでもなく、ただ隣にいる祐樹のことを考えていた。顔を上げると、祐樹はまだ目を閉じて、何か祈っている。
(真剣な表情だな)
横顔を眺める。真横から見るのは初めてかも知れない。こんな表情、真剣な表情は初めてだ。きりっとして、意外とかっこいい系かもしれない。正面から見ると、そうでもないんだけどな・・・
長いお祈りだった。ようやく祐樹が顔を上げる。
「行こうか」
祐樹が腕時計を見る。
「明けたよ」
「そっか」
「明けましておめでとうございます」
祐樹が、さっきの真剣な表情とはうって変わって笑顔で言う。
「おめでとう。今年もよろしく・・・って、今日と明日だけか」
「今年もよろしくお願いします」
祐樹はあえてそう付け加えた。明日で終わり、ということは一旦忘れて・・・ということか。
「寒いから早く帰ろう」
祐樹が言った。
(年越し参りに行こうと言い出したくせに)
でも、そんな祐樹をかわいい、と思う。
祐樹が俺の手を握った。俺達は手をつないで家に帰った。
「体冷えたでしょ。お風呂、入っちゃって」
家に帰ったとたん、祐樹が言った。
「ああ、今からお湯入れる」
「もう、入ってるよ」
祐樹がお風呂場を覗いて言った。
「お湯、入れてったのか?」
「タイマーだよ。家出る前に設定しといたから」
俺よりも、この家のことをわかってるのか、こいつは。
「タイマー設定なんてできるのか・・・家の風呂」
「知らなかったの?」
祐樹が大げさな表情をする。
「うるさいなぁ・・・」
俺は洗面所で服を脱ぎ、バスルームに入る。
「バスタオル、ここ置いとくね」
バスルームのドア越しに祐樹が言った。
「ああ」
そして俺は湯船に浸かった。
(なんだか・・・つむじ風みたいな奴だな)
もちろん、祐樹のことだ。
(会ってまだ1日も経ってないのに・・・前からずっと恋人だったような気がする)
それがレンタルという仕事をしている祐樹のテクニックなのかも知れない。
(でも・・・いいよな、恋人がいるって)
少しにんまりした。
「背中、流してあげる」
祐樹の声がした。ドアが開く。祐樹が入ってきた、
「お前、なんで裸だ?」
「お風呂、服着たまま入るの?」
当たり前だ。いや、そうじゃなくて・・・
「背中だけ流しに入ってきたんじゃないのか?」
「なんで・・・一緒に入ろうよ」
ちょっとすねてみせる。しかし、俺は祐樹の股間に目が釘付けになっていた。
「どこ見てるんだよ」
「い、いや・・・」
祐樹が大げさに恥ずかしがってみせる。いや、実際に恥ずかしいのかもしれない。彼の股間には毛がなかった。
「毛、剃ってるのか?」
「やっぱ、見てるじゃん」
確か、13才。生えてて当たり前だろう。
「まだ生えてません」
「まだって・・・お前、13だろ、確か」
「だから・・・言わないでよ。ちょっとコンプレックスなんだから」
祐樹は恥ずかしがって股間に手を当てる。俺はその手をどけようとする。
「やだって」
こっちにお尻を向ける。きれいなお尻だった。背中からお尻にかけてのラインも美しい。
「きれいな体だな」
俺は思った通りのことを口にした。
「何言ってるんだよ・・・恥ずかしいよ」
少し顔が赤い。
「そっちに寄って」
俺を湯船の片隅に追いやると、狭い湯船に祐樹も入ってきた。俺の足の間に座る。そして、背中を俺に預ける。
「はぁ・・・」
大きな声でため息をつく。俺は、祐樹の腹の前に手を回す。ゆっくり手を下げていく。そして、無毛の股間を触る。
「渉さんは、いつ生えたの?」
やっぱり気にしているらしい。
「覚えてないけど・・・小6くらいだったような気がする」
「やっぱり・・・僕、遅いよね」
「学校で何か言われるの?]
「見られないようにしてるから」
俺は無毛の股間をなでた。
「でも、これもいいかもしれないよ。きれいだし」
「大人になっても生えてこなかったら・・・どうしよう」
「大丈夫だよ」
気休めにもならないだろうが・・・
そんな話題を変えるために、ということを口実にして、俺は祐樹のペニスを握った。その瞬間、祐樹が少し体を硬くする。
「大丈夫だよ」
祐樹の耳元で言った。しかし、祐樹は動かない。俺はゆっくりとペニスを握った手を上下に動かす。祐樹は何も言わないが、徐々にそのペニスは硬さを増す。
「人に触られるの、初めて?」
こくっと頷く。俺の手の中で、祐樹のペニスは完全に勃起している。
「あ、あの・・・」
こらえきれないのか、少し焦ったような声を出す。
「か、体、流さないと」
(初めてなんだから、仕方ないか)
俺は少し笑って、祐樹を解放した。祐樹は勃起したペニスを隠そうと、手を股間に当てて、湯船から出る。
「渉さん、お背中お流しします」
俺も湯船から出て、祐樹の前に座る。祐樹が俺の背中を流す。時々、熱い物が俺の背中に当たる。
「まだ勃起してるのか?」
そう尋ねると、祐樹は恥ずかしそうにする。
「今度は俺が洗ってやるよ」
祐樹は俺に背中を向ける。そんな祐樹に前を向かせる。手を股間からどけさせる。俺は祐樹の体を洗う。まだ勃起したままのペニスも含めて。
さすがにお風呂から上がる頃には、祐樹のペニスも普通の状態に戻っていた。バスタオルでざっと体を拭いて、その美しい体にバスタオルを巻き付ける祐樹。俺も風呂から上がる。祐樹はパジャマを持ってきていなかったので、俺のを貸してやる。ぶかぶかのパジャマを着た祐樹は、一段と可愛く見えた。
「俺はソファで寝るから、お前は俺のベッドで寝ればいいよ」
風呂から上がって一休みすると、どちらかというと朝に近い時間になっていた。
「渉さん、ベッド使って下さい」
「遠慮するなって」
俺は予備の布団を押し入れから引っ張り出そうとした。祐樹がそんな俺を止める。
「遠慮じゃないですよ」
「いいから、ベッドで寝ろ」
「だから、ベッドで一緒に寝ちゃだめですか?」
ちょっと意外な申し出だった。
「い、いや、それは・・・その・・・」
「恋人なんだから、いいですよね?」
そう言って祐樹は笑顔を見せる。そんな笑顔を見せられれば、断ることなんかできなかった。
「二人で寝るには狭いぞ?」
「いいですよ。渉さんに抱きついて寝ますから」
(もしも、わかって言ってるとしたら・・・悪魔だな、こいつ)
そう思った。
ベッドに入ると、すぐに祐樹は俺の胸にしがみつくようにしながら寝息を立て始めた。
(本当に、こんな子が恋人だったらな・・・)
俺は祐樹の体温と重みを感じながら、睡魔と戦っていた。眠ってしまうのはもったいない、そんなひとときだった。が、やがて俺も祐樹を抱きしめながら眠りに落ちていた。
目が覚めた。
祐樹はすでにベッドにはいなかった。美味しそうな匂いがしている。俺がキッチンに行くと、祐樹がエプロンを着けて食事の用意をしている。
「あ、おはようございます」
「おはよう」
そう答えてから時計を見た。すでにおはようの時間ではなかった。
「もう・・・昼だな」
昨日の・・・というか、今朝ベッドに入ってから、7時間ってとこか。けっこう寝たわりには、まだ眠い。
「お餅、いくつ食べます?」
「そうだな・・・」
(そうか、あの匂いはお雑煮か)
リビングを見ると、こたつの上にお重が置いてあり、その手前に食器や箸が2セット並べて置いてある。
「なんか、正月らしいな。こんなの、家にあったか?」
正月らしい紅白の袋に入った箸には見覚えがない。
「今朝、コンビニ行って買ってきました」
俺は祐樹を後ろから抱きしめる。祐樹が手を止めて俺に言う。
「改めて・・・明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」
「明けましておめでとう。今年も・・・」
(明日までだけど)
「よろしく」
俺は祐樹の耳元でささやいた。
「じゃ、早く着替えて顔洗って下さい」
俺は祐樹に言われるまま、着替えを取りにベッドルームに戻った。
「じゃ、渉さん、座って」
祐樹が俺をこたつに導く。
「美味しいかどうか分からないけど」
そう言いながら、祐樹は3段重ねのお重を1段ずつ並べる。美味しいかどうかは分からないが、少なくとも見た目はとてもきれいに詰められている。
「じゃ、いただきます」
俺は箸を取る。祐樹はキッチンに戻ってお雑煮の準備をしている。
「どう?」
お雑煮を持ってきて祐樹が尋ねる。
「美味しい、すごく」
そう言うと、うれしそうに笑う。
「特に黒豆、上手く煮えてる」
「それ、買ってきたやつだから」
少しだけ、祐樹が口を尖らせる。
「お前が作ったのも美味しいって」
ご機嫌取りじゃない。祐樹が作ったとか買ってきたとか関係なく、どれもこれも美味しかった。食事がこんなに美味しいと感じたのはずいぶん久しぶりだ。
「よかった」
祐樹が喜ぶ。ただの少年の笑顔。ただのレンタル・・・でも、今は俺の恋人の笑顔だ。
「ほら、祐樹も座れ」
俺の横に座る。おせち料理の端から順番につまんでいく。
「うん、上手く出来た」
「美味しく出来てるよ」
二人でゆっくりと箸を進める。テレビでは、お正月のお笑い番組を放送しているが、そんな音は耳に入らなかった。
「昨日はちょっと寒かったけど、今日はいい天気だね」
外は晴天、少なくとも家の中からは暖かそうに見える。
「そうだな。後でちょっと散歩にでも行くか」
「うん」
うれしそうに祐樹が頷く。
「じゃ」
俺は昨日のうちに準備して、ポケットに入れておいたお年玉を祐樹に差し出した。
「え、でも・・・」
「いいじゃないか、お正月なんだし」
「じゃ、ありがとうございます」
祐樹は両手で押し戴いた。
「お返し」
そう言うと、両手で俺の顔を挟んで、キスしてくれた。
|